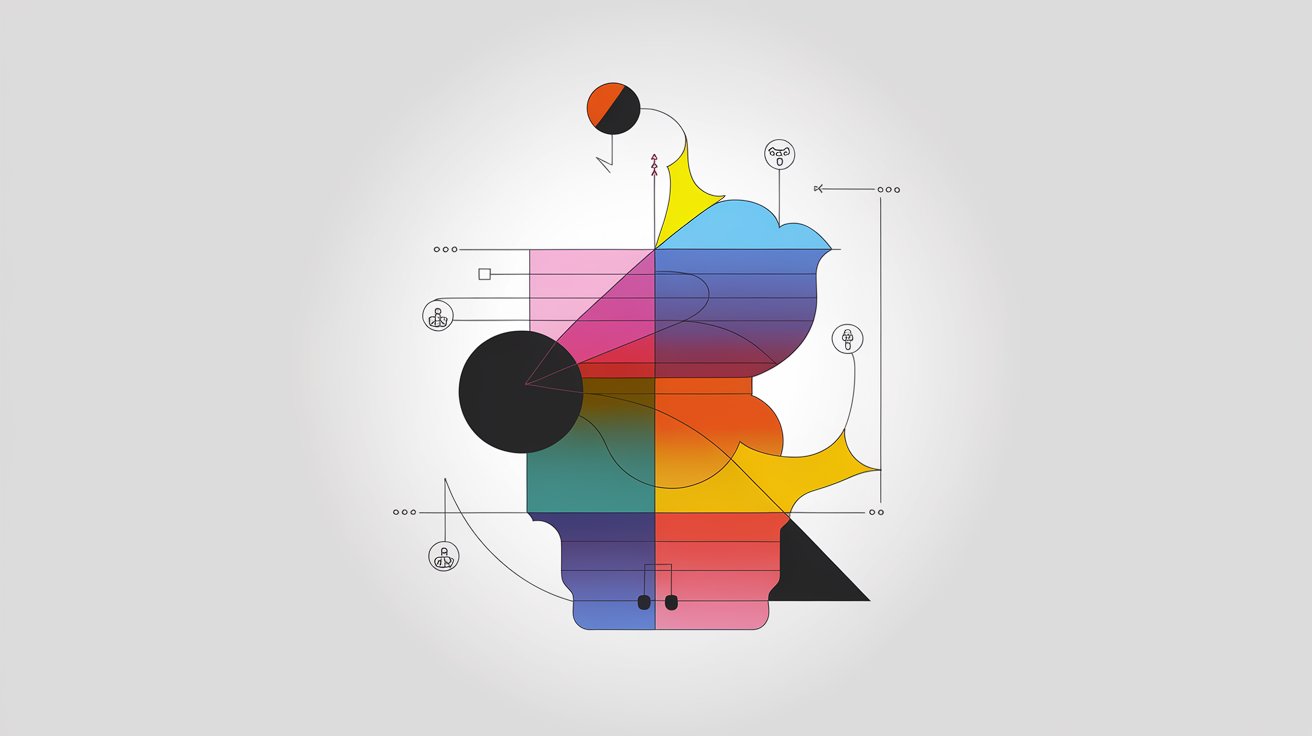
プロダクト開発を進める過程で、ユーザーの視点を踏まえた要件定義を行う際に、なかなか全体像がつかめず苦労した経験はありませんか。ユーザーの利用実態を正確に把握して開発を進めたいと思っても、組織内部のプロセスや関係者の都合など、さまざまな要素が絡み合って複雑化し、最終的に要件定義の段階で抜け漏れや認識の違いが生じてしまうことは珍しくありません。
そんなときに活用が注目されているのが「サービスブループリント」という手法です。本記事では、サービスブループリントを活用した要件定義について、詳しく解説していきます。ユーザー体験を正しく捉え、スムーズなプロダクト開発を実現するために、サービスブループリントがいかに有効なツールとなり得るのか、その背景や具体的なメリット、そして活用のステップを詳しくご紹介します。
サービスブループリントとは何か
サービスブループリントは、ユーザーがサービスや製品を利用する際にどのような体験を得るのかを、表面に現れる「顧客接点(タッチポイント)」だけでなく、企業内部や提供者側のバックエンドプロセスまで含めて一枚の可視化された図にまとめた設計図のようなものです。通常のフローチャートよりも詳細に、ユーザーの行動やタッチポイント、組織内部のアクション、サポートシステムなどを明示していくため、サービスの構造や流れが立体的に把握できます。
この手法は1980年代にサービスマーケティング分野の研究から着想を得ており、近年はユーザーエクスペリエンス(UX)向上のために取り入れられるケースが増えてきています。サービスブループリントの基本概念では、ユーザーが行うアクションと、それに対応する企業側の活動を分けて記述するという特徴があります。ユーザーが予約、購入、問い合わせといった行動をとる裏には、顧客が直接目にしないスタッフのオペレーションやシステム間の連携が必ず存在します。
サービスブループリントでは、こうしたバックステージ(舞台裏)の動きを視覚化することで、チーム全体が「ユーザーが何を必要としているのか」「そのときに企業はどんな手順を踏んでサポートすべきか」を一目瞭然で把握できるようになるのです。
サービスブループリントが求められる背景としては、デジタルサービスの多様化とユーザー体験の複雑化が大きく影響しています。スマートフォンからのアクセス、オンライン決済システム、SNSでのフィードバックなど、ユーザーとサービスの接点はかつてないほど多岐にわたります。従来のプロダクト開発プロセスでは、担当部署や機能ごとにタスクを切り分けて計画を進めることが多いため、ユーザー体験全体を見通すのが難しい状況に陥りやすくなりました。
そこで、サービスブループリントを用いることで、サービスの全体像を俯瞰して要件を洗い出し、開発チームだけでなくカスタマーサポートやマーケティングなどの部署と情報を共有しやすくしています。
サービスブループリントと他のUXデザイン手法との違いは、カスタマージャーニーマップが主にユーザーの体験や感情の流れに焦点を当てるのに対し、サービスブループリントはユーザーの行動と企業内部のアクションを対応づけて描き出す点にあります。いわば「表舞台と裏舞台を一体でマッピングするツール」がサービスブループリントであり、単なるユーザー目線だけでなく、サービス運営に携わるステークホルダーそれぞれの役割や負荷、情報の受け渡しなどを把握するのに適しています。
そのため、プロダクト開発における要件定義の精度を高めるだけでなく、将来的なスケールアップや運用体制の変化にも柔軟に対応しやすいのが特長です。
サービスブループリントがもたらすメリット
サービスブループリントを導入する最大のメリットは、顧客体験の向上とプロセス改善を同時に実現できる点です。要件定義の段階から、ユーザーが抱える課題や期待を細かく洗い出し、その裏で企業側が実施すべき行動を明確化することで、無駄のない動線やエラーを減らす設計が可能になります。
たとえば、ユーザーがオンライン上のフォームで予約を完了する際に必要とされる情報が、実は別の部署でもう一度手入力されている場合など、非効率的な重複作業に気付きやすくなります。このようにサービスブループリントは、顧客体験のスムーズ化と組織内部のプロセス最適化を同時に進められるため、サービス全体の品質向上につながります。
もう一つの大きなメリットは、チーム間コミュニケーションの向上と要件定義の効率化です。要件定義が複雑になるほど、多様な専門分野や部署が関わり、情報のやりとりが増えていきます。サービスブループリントを活用することで、誰がどのタイミングで何を行うかが可視化されるため、プロジェクト全体における認識のずれや連携ミスを減らせます。
結果として、仕様変更やトラブルによる大幅なリスケジュールを最小限に抑え、スムーズな要件定義の完了と開発の着手が可能になります。特に海外拠点との共同プロジェクトを行う場合など、言語や文化の違いも踏まえて情報を共有する際には、視覚的な共通言語としてサービスブループリントが大きな力を発揮します。
さらに、サービスブループリントを導入しておくことで、将来の拡張性を見据えた構造的アプローチを取ることができます。新たな機能追加や新規プロダクトの投入を検討するとき、すでに作成したサービスブループリントを基盤として「ユーザー体験とバックエンドの関係をどのように変化させるか」を俯瞰的に考えることができるようになります。拡張や変更によって、既存のプロセスやシステムとの整合性を担保しながら柔軟に対応できるため、長期的な事業戦略にも貢献する点が海外のプロダクトマネージャーやスタートアップ企業からも高く評価されています。
要件定義におけるサービスブループリント活用のステップ
要件定義にサービスブループリントを活用するにあたって、まずは現状把握のための準備作業を入念に行うことが重要です。プロダクトやサービスに関わる部署や関係者を幅広く巻き込み、まずはユーザー視点での現状調査を行います。アンケートやインタビュー、サービスのログ解析などを通じてユーザーの行動と課題を洗い出し、どのような利用シナリオがあるかを明確にしておくと、後々ブループリントを作成する際に抜けや漏れが少なくなります。
次に、ユーザータッチポイントとバックエンドの洗い出しを行います。ユーザーがサービスや製品とどのような接点を持つのかを、時系列に沿って整理します。たとえば、ECサイトであれば、トップページに訪問、商品検索、カートに追加、決済、商品の受け取り、アフターサービスなどの流れが考えられます。それぞれの段階においてユーザーがどんな行動を取るか、感情やモチベーションはどう変化するかを記述するだけでなく、企業側(運営チームやシステム管理部門など)が裏でどのような処理を行っているのかも合わせて書き出します。ここでは、顧客データベースへのアクセスや在庫管理システムとの連携、決済プロバイダーとのやりとりなどのバックエンドプロセスを明確化することが不可欠です。
このようにして整理した情報をサービスブループリントとして視覚化したら、組織内部とのすり合わせを行います。プロダクトオーナー、デザイナー、エンジニア、カスタマーサポートなど、多様なステークホルダーが一つの図面を基にディスカッションを行うことで「このプロセスではユーザーとのやり取りをもっとシンプルにできないか」「ここで不必要な作業が発生していないか」といった改善点を見つけやすくなります。ここで重要なのは、単に理想像を描くだけで終わらせるのではなく、現実の組織やシステムの制約を踏まえて実行可能な改善策を合意することです。現場レベルの意見や制限事項を踏まえることで、より実践的な要件定義をまとめられるようになります。
そして、サービスブループリントを活用した後は効果測定と次回へのフィードバックを必ず行うようにします。具体的には、改善策を実装してからのユーザー満足度の向上や、コールセンターへの問い合わせ数の変化、開発工程のトラブル発生率などをモニタリングし、期待通りの結果が得られているかを定量的・定性的に評価します。
サービスブループリントは一度作成して終わりではなく、継続的にアップデートすることで、プロダクトの成長とともにユーザー体験と組織プロセスを最適化していく指針となります。
プロダクト開発における具体的な事例
既存サービスのリニューアルにおいても、サービスブループリントは有効に機能します。長年運営されてきたサービスでは、部署横断的に行われてきたカスタマイズや連携の履歴が複雑化していることが少なくありません。システム同士の連結に部分的なワークアラウンドが存在したり、特定部署だけで動いているスクリプトなど、いわゆるブラックボックスがあったりするケースもあります。
そうした「慣習化した複雑さ」を可視化する手段として、サービスブループリントが役立ちます。ユーザーが触れる部分だけでなく、裏で稼働するプロセスを一つひとつ棚卸しして図示することで、どの部分を優先的に見直すべきか、あるいはどこを残したままにするか、といった判断がしやすくなります。
グローバル展開を視野に入れた場合にも、サービスブループリントは効果的です。ユーザーの国や地域が変わると、物流や決済方法、法規制、サポート体制など、サービスのバックエンドにおける要素が変動します。そうした多国籍な要件を含む際にも、サービスブループリントを活用しておけば、どのプロセスを国ごとにカスタマイズすべきか、共通化できる領域はどこかなどが可視化され、スケールアウトが容易になります。
特に英語圏以外のマーケットに進出する場合は、利用する言語や接客スタイルなども変化しますが、サービスブループリントを通じて全体像を把握しておけば、開発チームやビジネスサイドの混乱を最小限に抑えることができます。
サービスブループリントの作成ツールとポイント
サービスブループリントの作成には、MiroやMural、Lucidchart、Createlyなどのオンラインコラボレーションツールがよく用いられています。特にリモートワークが普及した現在では、チームメンバーが地理的に離れていてもリアルタイムに図を共有しながら編集を進めることができます。ツールを選ぶ際には、ステッカー機能やコメント機能が充実しているものを選ぶと便利です。ユーザータッチポイントとバックエンドを整理する段階で、関係者が自由に付箋を貼り、疑問点や追加情報をリアルタイムで書き込める環境を整えると、よりスピーディにディスカッションが進みます。
カスタマージャーニーマップとの違いを意識した設計上の注意も忘れてはいけません。カスタマージャーニーマップはあくまでユーザーの体験や感情の流れを中心に描くため、バックエンドプロセスやステークホルダーの役割分担を詳細に示すには向いていません。一方でサービスブループリントは、ユーザーが目にする「表」の世界と、企業内部の「裏」の世界とを一体化してマッピングします。
そのため、情報量が多くなりがちで、無秩序に要素を書き込むと混乱を招きます。作成時には、ユーザーアクションの列、フロントステージで行われる業務の列、バックステージの列、サポートプロセスやシステムの列など、レイヤーごとに整理して描くようにするとわかりやすくなります。
サービスブループリントは、作成した後の運用フェーズも非常に大切です。一度作っただけで終わりではなく、定期的に見直しや更新を行い、実際の業務フローやユーザー行動との乖離がないかをチェックすることが求められます。特に、アジャイル開発やリーンスタートアップ的なアプローチでプロダクトを改善していく場合は、ユーザーのフィードバックや新機能の導入に伴ってプロセスが変化しやすいです。その都度、サービスブループリントを最新版にアップデートしておくことで、今後の要件定義やプロジェクト推進の際に活用できる“生きた資料”として維持できます。
まとめ
サービスブループリントは、プロダクト開発の要件定義を精度高く行うために、有力な手段として注目を集めています。ユーザーが感じる価値や利用シナリオを丁寧に拾い上げながら、それを支える組織内部のプロセスやシステム連携を同時に見える化することで、抜け漏れの少ない要件定義を実現できるからです。
要件定義の段階からサービスブループリントを取り入れ、プロダクトと組織全体の動きを把握しながら改善を進めていくことで、一貫性のあるサービス体験と効率的な運用体制を実現できるはずです。