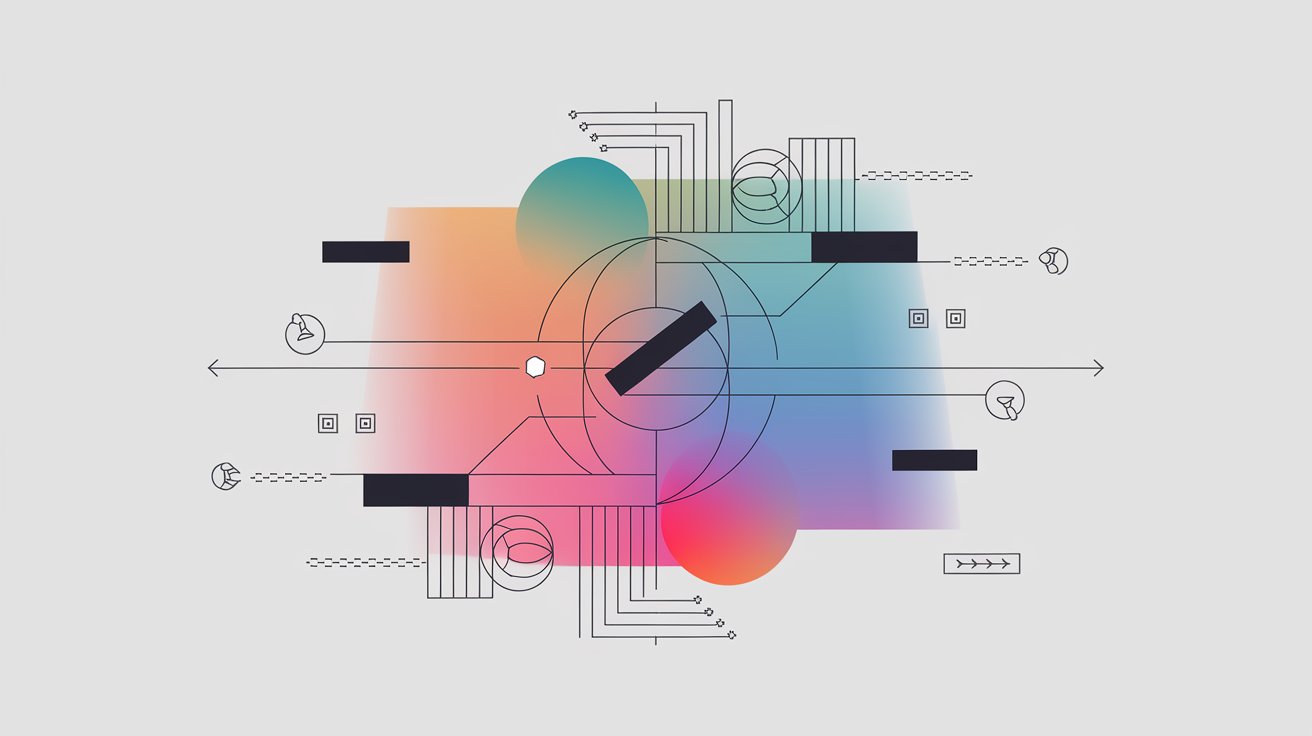
要件定義の段階で、クライアントから要望をヒアリングしてみたものの、肝心な要素が抜け落ちてしまい後々トラブルになることはありませんか。あるいは、チーム内で情報の共有がうまくいかず、いつの間にか開発範囲が肥大化していた経験はありませんか。こうした「いつ、どこで、何を、どうするのか」が明確になっていない状態を放置すると、最終的な成果物の品質や納期、コストに大きな影響を及ぼしかねません。そこで注目されているのが、海外のプロジェクト管理でも活用されている「5W1H」です。本記事では、要件定義における5W1Hの活用方法と具体例について掘り下げていきます。
5W1Hとは何か
5W1Hとは、Who、What、When、Where、Why、Howという六つの問いかけによって物事を多角的に整理する分析手法を指します。もともとはジャーナリズムの取材手法として広く知られていましたが、現在ではビジネスシーンや問題解決の場面でも幅広く活用されるようになりました。
5W1Hの特徴
5W1Hの最大の特徴は、それぞれの問いが単なる表面的な情報を引き出すだけでなく、目的や背景、具体的な行動レベルに至るまで深く踏み込むきっかけを与えてくれる点にあります。海外のデザイン思考やイノベーション支援の分野では、5W1Hを応用した「6 Questions」という枠組みが用いられるケースもあり、より包括的にユーザーのニーズや開発目標を洗い出しています。問いを形式的に並べるだけでなく、プロジェクトの目的に合った順番や深度で活用し、抜け漏れや曖昧さを早期に可視化することが大切です。
6 Questionsについて
「6 Questions」とは、UX(ユーザーエクスペリエンス)リサーチやデザイン思考のプロセスで用いられるフレームワークの一つで、プロジェクトや課題を多面的に整理するために「Who, What, When, Where, Why, How」という六つの問いを軸に検討していく手法です。5W1Hと同じ構成ですが、UXの観点から要件やターゲット、利用シーンをより具体的に描き出すことに重きが置かれている点が特徴です。
この「6 Questions」では、たとえばサービスを利用するユーザーが「誰(Who)」なのか、そのユーザーに「何(What)」を提供すべきか、利用シーンは「いつ(When)・どこで(Where)」起こり得るのか、そもそも「なぜ(Why)」そのサービスが必要なのか、そして最終的に「どのように(How)」実現するか、といった視点を一貫して洗い出します。こうした基本的な問いを段階的に深掘りすることで、ユーザーが本当に求めている価値や課題の優先順位を明確化し、開発プロセスの初期段階からチーム全体の認識を合わせやすくなります。特に海外のUXリサーチやサービスデザインの分野では、短い期間で効率的に本質的な課題を洗い出す方法として、この「6 Questions」アプローチがよく採用されています。
要件定義との親和性
要件定義のフェーズでは、関係者や目的、実装手段を含むあらゆる情報を5W1Hに沿って整理することで、プロジェクト全体を俯瞰しやすくなります。海外のプロジェクト管理やコンサルティングの現場では、新規サービスを立ち上げる際に「誰の課題を解決するのか」「なぜこの開発が必要なのか」といった観点を最初に確定させ、それを具体的な機能要件にまで落とし込んでいきます。こうすることで、後から「想定外のステークホルダーがいる」「実装の優先順位が不透明」という混乱が生じるリスクを抑えることができます。
5W1Hがもたらすメリット
要件定義においては、5W1Hが持つ網羅性と柔軟性が特に有効に働きます。プロジェクトの目標を正確に捉えるだけでなく、開発工程全体を見渡しながら要件を精査できるため、海外のイノベーション事例でも中心的な手法の一つとして取り入れられています。問題解決を図るうえで悩ましい「要件の優先度があいまい」「ステークホルダーの意見が食い違っている」といった状況も、5W1Hを通じて丁寧に洗い出すことで、より具体的で合意形成しやすい要求仕様に結びつけることができます。
5W1Hを要件定義に落とし込む方法
Who: 関係者の洗い出しと役割の明確化
要件定義の最初のステップとして、プロジェクトに関わるすべてのステークホルダーを整理します。海外のプロジェクトでも、キックオフやワークショップを活用して関係者の期待値を共有することが多いです。利用者や運用担当、管理部門など、さまざまな角度から「誰が最も影響を受けるのか」「誰が決裁権をもっているのか」を明確にし、後々の想定外の要求や軋轢を防ぎます。
Why: プロジェクトの目的や意義を掘り下げる
新しいシステムやサービスを立ち上げる際に、なぜその要件が必要なのかを徹底的に問い直します。海外のイノベーション手法では、この「Why」を早期に共有し、チーム全体の目的意識をそろえる傾向が強いです。目的があいまいなまま進めてしまうと、開発途中で「そもそも求めていたものと違う」という事態になり、成果物の価値を正しく伝えられなくなるリスクが高まります。
What: 必要な機能やサービスの具体化
要件定義の肝となるのが、「どのような機能やサービスを実装するか」の具体化です。UXリサーチ手法などを参考にしながら、ユーザーの課題や不満をどの程度解決できるのか、既存システムとの差別化をどう図るのかを検討します。ユーザーストーリーの形で利用シーンをイメージし、後から発生しそうな手戻りを減らすようにまとめます。
Where: 使用環境や状況を多角的に検討する
システムやサービスが実際に使われる場所・シチュエーションを考慮します。リモートやフィールドなど多様な環境で利用する可能性があるなら、それぞれに合わせた接続環境やUI設計が必要になります。グローバルに展開しているプロジェクトの場合は、言語や時差、通信インフラの違いまで視野に入れ、早い段階で考慮しておくことが重要です。
When: スケジュールと優先順位の明確化
プロジェクトの進行計画や優先度を整理します。アジャイル開発が浸透している海外企業では、短いスプリントごとに何をリリースし、いつユーザーからフィードバックを得るのかを設定する事例が多いです。要件定義時にこのリリースサイクルを意識し、最低限必要な機能から開発していくことで、追加的な要件も柔軟に取り込めるようになり、全体の工数が抑えられます。
How: 技術や実装手法の選定
決定した要件をどのように形にするのか、開発言語やフレームワーク、クラウド環境などの技術的アプローチを検討する段階です。ビジネス価値と技術リスクを比較しながら、初期段階でPoC(概念実証)を実施して大幅な仕様変更が必要にならないか確認するなど、要件定義の時点でHowを十分に検証し、ゴールを達成できる手応えを得たうえで開発に着手することが大切です。
柔軟な進め方と全体最適の意識
5W1Hを要件定義に活用する場合、必ずしもWho → Why → What → Where → When → Howの順番で進める必要はありません。たとえば顧客ニーズを最重視したい場合は「What」や「Why」から入るほうがスムーズなこともありますし、多数のステークホルダーが絡む大規模プロジェクトなら「Who」を最初に徹底的に洗い出すほうが適切なケースもあります。いずれにしても、六つの問いを通じて多面的にプロジェクトを点検することで、想定外の手戻りや開発中の迷走を最小化できるのが5W1Hの大きな強みです。
まとめ
要件定義の時点で十分な質問を行わずにプロジェクトをスタートさせると、後から根本的な問題に気づいて修正に時間を取られてしまうことが少なくありません。5W1Hの手法を取り入れると、関係者や目的、環境、優先順位を明確化しやすくなり、問題解決の糸口をつかむだけでなく、実際の実装フェーズでもスムーズに作業を進めることができます。海外のプロジェクト事例を参考にしながら、日本の開発現場でも効果的に5W1Hを取り入れ、より確実で無駄のない要件定義を目指してはいかがでしょうか。